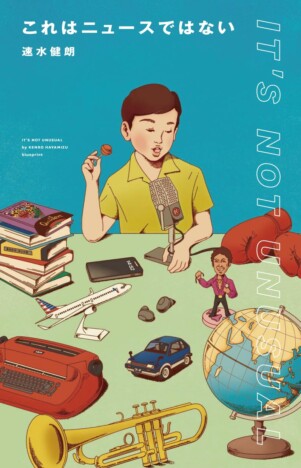映画業界に生きる“いかがわしい人々”の愛嬌ーー『下衆の愛』に滲み出た映画愛を読む

「一回味わうと抜け出せねぇぞ。シャブよりもタチが悪いからな、映画っていうのは」──古舘寛治演じる映画監督が、新人女優にそう囁く通り、『下衆の愛』は映画を愛し、その底なしの深みに耽溺してしまった人々をシニカルに取り上げたコメディ映画である。「監督とプロデューサーは全員クソヤロー!」と銘打たれているように、芽が出ないまま性格をこじらせた“下衆”な映画人たちの姿がブラックかつコミカルに描かれる。主演は2015年映画出演本数11本を誇り現在最も注目される俳優・渋川清彦。野心的な新人女優役を岡野真也が務め、ある種ファム・ファタールとも言える役柄に挑戦している。ほか、細田善彦、忍成修吾、でんでん、内田慈、津田寛治、古舘寛治、木下ほうか等、近年の日本のインディペンデント映画を中心で盛り上げている個性豊かな俳優が数多く出演。第28回東京国際映画祭「日本映画スプラッシュ」部門、第45回ロッテルダム映画祭での上映を経て、4月2日より公開される。すでに海外配給や各国の映画祭での上映も決定している。近頃、“下衆”という言葉が流行語のようになっているが、本作からは不快な印象をほとんど受けない。むしろ、卑しく品性に欠いた行動を取ってしまう人間に対して、決して愚かな面を断罪して咎めようとするのではなく、もっとおかしみや愛嬌を見出そうとしているように思える作品である(それは作り手たちが、オックスフォード英語辞典に“下衆”という日本語を「下劣なこと、もしくはその人、しかし愛嬌がある」という意味合いで申請したことからもわかるだろう)。(参考:「GESU(ゲス)」を英語辞典に採用申請へ 「下衆の愛」の渋川清彦「ゲスは悪い言葉ではない」)

映画は、前の晩に関係を持ちそのまま眠ってしまったと思しき真っ裸の男女が、朝になり目覚めるところからはじまる。男が自宅に連れ込んだスタイルの良い女(卯水咲流)は先に起き、そそくさと衣服を着て荷物をまとめると、男がまだ寝ぼけ眼のなか、言葉少なに帰っていく。生々しい雰囲気で自堕落な生活を送っている39歳の男の生態が捉えられるが、この男こそ主人公の自称・映画監督のテツオ(渋川清彦)だ。テツオは過去に映画祭で受賞した経験を持つことが唯一の自慢で、その後は満足に映画を撮っていないまま、現在まで実家に寄生しつづけており、監督とは名ばかりの、いわばパラサイト・ニートである。
テツオは後輩で助監督も務めるマモル(細田善彦)がハメ撮り(!)して稼いできたお金をピンハネしながら、役者志望者を集ってはワークショップを自ら主催している。彼の周りには、うだつのあがらない俳優や胡散臭いプロデューサーたちばかりが集まっている。飲み会で知り合った監督やプロデューサーに近づいては枕営業を試みることに賭ける──寝る前にその相手がどのような実績があるか、最近は活動しているのかなどを入念に調査する──女優の響子(内田慈)がいれば、逆に自分の作品に出してやるとそそのかして女性に性的行為を求める監督やプロデューサーがいる。このように、本作に登場する映画業界の人々の人物像は、それぞれ売れない監督や俳優たちの戯画になっているのである。そこには、「週刊プレイボーイ」ライターを経て、脚本家、映画監督となったキャリアを持つ内田英治らしいゴシップ的な俗っぽい観点があらわれているだろう。
新人女優にすぐに手を出す映画監督、ハメ撮りで生計を立てる助監督、枕営業にチャンスを賭ける打算的な女優、セクハラ&パワハラするプロデューサー……『下衆の愛』は、観客がたしかにどこかで噂を見聞きしたことがあるような映画業界のダーティなイメージを少し誇張的に戯画化してコメディ・タッチの中で取り扱っている。たとえば、バンドマンの彼氏の安定を求めない“ロックな“生き様に惚れていたのに、彼から音楽を辞めて働くと宣言されてしまった女の子カエデ(山崎祥江)のキャラクター設定は(いささか観念的ではあるが)好ましく映る。バンドマンの彼氏がほかの男たちと同じ“つまらない大人”になってしまったことに失望した直後、彼女は居酒屋のトイレでテツオが女を連れ込んで大胆にも行為に及んでいるところに遭遇し、彼に一目惚れしてしまうのである。あるいは、とにかく映画にはふんだんに濡れ場を盛り込め!と煽っていた団塊世代のプロデューサー貴田(でんでん)が、突然、裸よりも「犬や猫が死ぬ映画が今は売れる」と言い出す様は、実に粗雑なプロデューサーのいかがわしい面があらわされている。この多分にコミカルだけれど、実際にいるかもと思わせる塩梅でキャラクターを造形しているのが、内田の上手いところだろう。また、売れない俳優の一員に元劇団員だったことで知られる芸人のマツモトクラブが紛れていたり、テツオの妹でネットに自身のエロ動画をアップしている女子高生をAV女優の川上奈々美が演じていることも、さらなる説得力をもたらしているかもしれない。こういった細部まで目を配らせた俳優陣へのアプローチとひとりひとりの好演が、映画におかしみと愛嬌を宿らせているのである。
しかし思うに、テツオという人物を見ていると、彼にとってワークショップを開くことは映画を作るためではなく、むしろ金を集めたり女と出会うためのものでしかなくなっているのかもしれない。いまやテツオは、ワークショップに参加してきた若い女の子や才能のない女優と寝るための名目として、「映画」の名を使っているだけに過ぎないのだ。テツオの下衆さは、彼のだらしなさや甲斐性のなさにあるのではなく、映画への冒涜した態度にあるのである。かつて抱いていた映画製作への情熱を失いかけていたテツオの元に、ふたりの才能ある若者──脚本家志望のケン(忍成修吾)と女優志望のミナミ(岡野真也)──が訪ねてきたことで、徐々に彼はその胸の内にあった映画作りへの純真な気持ちを再燃させていく。

テツオが稽古場で新人のミナミに対して、手をグーにしたら「好き」と、パーにしたら「嫌い」と言葉を発させるよう演技指導をする場面は、彼のミナミへの熱心な期待を感じさせると同時に、その行為の中に見られるモラル上の問題をもアイロニカルに示唆する印象的な場面だ。演出家として納得のいく芝居がまだまだ引き出せていないと考えるテツオは、いきなり彼女の胸を揉みしだく。すると、ミナミは激しい嫌悪感を露わにするが、それによって前よりもはるかに憎しみのこもった「嫌い」という言葉を涙を流しながらもテツオにぶつけられるようになる。つまり、テツオは真に迫った演技を引き出すために胸を揉んだのだ。“下衆”な行為でありながら、結果だけを見ればそれは演技指導の効果を発揮しているとも言うことができるのかもしれない。しかし、果たしてそれはセクハラではないのだろうか……? そんなことを考えさせるのだ。
また、稽古場でミナミに対して熱心に演出するテツオの後ろでは、それに何の興味関心もないような目で彼女の演技を見ているほかの役者たちがいる。ここではほとんどの人物が、損得のためでしか人を見ていないのだ。映画のためにいつのまにか監督やプロデューサーは権力を振りかざすようになり、女優は映画の仕事を得るためなら進んでその犠牲者にすらなっていく。純真で汚れのなかった新人女優ミナミは、大物に取り入っていくことで横柄な売れっ子女優へとのしあがっていく──まるで罪を重ねていくかのように。

ここで興味深いのは、日本映画業界に巣食ういかがわしい人々やそれにまつわるエピソードの数々について、内田が自分の身近なスタッフや役者から見聞きしたもので創作したと言う一方で、渋川は本作を一種の「ファンタジー映画」と語っていることだ。自分の周りでこのような人たちを実際に見たことはない、というのがその理由である。たしかに上述したように、ありそうでなさそうな絶妙なリアリティラインで描かれているからこそ、観客はある種ファンタジー映画のようにして、映画人たちのひねくれた一途さを滑稽なものとして微笑ましく見ることができるのかもしれない。